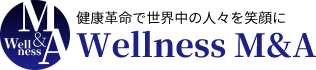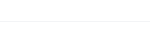事業継承を考える前に知っておきたい現状

接骨院・整体院とは何か
接骨院(整骨院)は、国家資格「柔道整復師」を持つ施術者が在籍し、打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼など、日常生活やスポーツ中のけがに対して、手技を中心とした治療を行う施設です。医療機関とは異なり、外科的な手術や投薬は行わず、人体の自然治癒力を引き出す施術によって回復を促す点が特徴です。
また、一定の条件を満たすことで健康保険の適用が認められ、特に地域では「軽度外傷のかかりつけ」としての役割を担っています。患者層は10代のスポーツ障がいから、慢性的な腰痛や肩こりを抱える高齢者まで幅広く、地域密着型の医療サービスとしての存在価値が高いといえます。
一方、整体院は国家資格を必要としない民間施術で、骨格・筋肉・神経のバランスを整えることで、姿勢改善や疲労回復、体のメンテナンスを目的としています。保険適用外のため全額自己負担となりますが、近年ではリラクゼーションや美容目的の利用者も増えています。
このように、接骨院は「治療」、整体院は「ケア・予防」という性質を持ち、いずれも地域の健康維持に欠かせない役割を果たしています。
接骨院・整体院のビジネスモデルの特徴
接骨院(整骨院)のビジネスモデルは、保険診療と自費診療を組み合わせた「複合型収益モデル」が基本です。
保険診療では、骨折・捻挫など外傷性の症状に対して療養費を請求し、安定した収益を確保します。一方で、制度改正や審査厳格化により保険収入が減少していることから、各院では自費施術メニュー(骨盤矯正、筋膜リリース、EMSなど)を導入し、単価アップや差別化を図る動きが広がっています。
このバランスをどう設計するかが、経営の安定性を左右する重要なポイントとなります。
整体院の場合は、完全自費制の単独収益モデルです。施術単価は高い傾向にありますが、リピート率と口コミによる集客力が業績に直結します。保険適用の制約がない分、メニュー開発やブランディングの自由度が高く、SNSを活用した集客や、サブスク型・回数券型など多様な料金設計が可能です。
ただし、施術者のスキルや顧客満足度への依存度が高く、「属人的な経営」になりやすい点が課題でもあります。
いずれの業態も、院長の技術力・経営判断・地域からの信頼が事業継続の鍵です。経営基盤を整え、仕組みで回る院づくりを進めることが、将来的な事業継承やM&Aを見据えた際にも大きな強みとなります。
必要な業許可・資格・人材について
接骨院(整骨院)や整体院を開業するには、資格・届出・人材体制などの要件を満たす必要があります。
特に接骨院(整骨院)は医療類似行為を行うため、法的な条件が厳格に定められています。
必要な資格
接骨院(整骨院)の開業には、柔道整復師の国家資格が必須です。
柔道整復師は厚生労働省の認可を受けた専門学校や大学で所定の課程を修了し、国家試験に合格することで資格を取得します。
資格名:柔道整復師(国家資格)
資格取得ルート:3年以上の養成課程修了 → 国家試験合格
業務範囲:打撲・捻挫・骨折・脱臼などの治療(医師の同意が必要な場合もあり)
一方、整体院では国家資格は不要で、民間のスクールや講習で技術を学ぶことが多いです。
ただし、国家資格がない場合、「治療」ではなく「リラクゼーション目的の施術」として運営する必要があります。
許可・届出の手続き
接骨院(整骨院)の開設は「許可制」ではなく、保健所への届出制です。
開業後10日以内に「施術所開設届」を提出する必要があります。
また、施術所には構造・衛生基準があり、施術室の広さ・照明・換気・待合スペースの確保などを満たさなければなりません。
| 必要な人材体制 | 届出内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 保健所 | 施術所開設届 | 開設後10日以内に提出(必須) |
| 消防署 | 防火対象物使用開始届 防火管理者選任届 |
建物の規模によっては必要 |
| 税務署 | 開業届出書 | 個人事業主として開業する場合 |
| 労働基準監督署 ハローワーク |
労働保険関係届出 | スタッフを雇用する場合 |
必要な人材体制
接骨院(整骨院)を運営するには、施術管理者(院長に相当)を配置する必要があります。
2024年4月以降は、柔道整復師の実務経験3年以上と施術管理者研修の修了が義務化されました。
施術管理者(院長)・・・施術全体の監督・保険請求管理・スタッフ教育
柔道整復師 ・・・施術実務・カルテ作成・患者さま対応
受付スタッフ ・・・予約管理・会計・接客
事務・経理スタッフ・・・請求業務・労務管理・帳票整理
整体院の場合は資格要件がないため、施術者の技術力と接客力がそのまま経営力に直結します。
いずれの業態でも、スタッフの定着と教育体制の整備が、長期的な経営安定につながります。
接骨院・整体院を取り巻く制度や保険制度の変化
近年、接骨院・整体院を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。
柔道整復師による保険施術の制度が厳格化され、経営面でも新しいルールや競争の波が押し寄せています。
保険制度の厳格化と料金改定
柔道整復師による保険施術では、請求内容の正確性がこれまで以上に重視されています。
施術の目的や回数、負傷部位の整合性まで細かく確認され、不備がある場合は支払いが保留・減額となるケースも少なくありません。
そのため、施術記録の精度向上と説明体制の整備が、日常業務の重要項目となっています。
経営環境の変化(インボイス制度・広告規制など)
2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書保存方式)では、法人や課税事業者との取引時にインボイスの発行が求められるようになり、登録の有無によって税務処理や取引条件が変わるケースもあります。免税事業者のままでは取引先が仕入税額控除を受けられず、契約を見直されるリスクもあるため、制度理解と対応方針の明確化が欠かせません。
また、広告については柔道整復師法やあはき法に加え、医療法によっても規制が強化されています。接骨院や鍼灸院などの非医療機関では「治療」「診療」といった医療行為を想起させる表現が禁止され、SNSやウェブ広告でも効果を断定する言葉や患者さまの体験談の過度な使用は罰則の対象となる可能性があります。こうした制度変化に柔軟に対応し、法令遵守と信頼性の高い経営体制を整えることが今後の持続的な運営に不可欠です。
デジタル化とマイナ保険証対応の義務化
医療・施術分野では、マイナ保険証によるオンライン資格確認の導入が進んでおり、接骨院や鍼灸院でも対応が実質的に必須となりつつあります。
これにより、受付や請求の効率化が期待される一方で、システム導入コストや運用負担も新たな課題となっています。
業界の市場動向と経営環境の変化

接骨院・整体院業界は、かつての拡大期を終え、いまや成熟と淘汰の時代に入っています。高齢化に伴う一定の需要はあるものの、療養費制度の見直しや人材不足、家賃や光熱費など固定費の上昇といった課題が重なり、経営環境は年々厳しさを増しています。人口構造や制度、競争環境が大きく変化するなかで、安定した経営を維持するためには、こうした変化に柔軟に対応できる力が求められます。市場の動きを正しく捉え、時代に合った経営モデルを築ける院こそが、これからの10年を生き抜いていく存在となるでしょう。
全国の施設数と人口あたりの接骨院数
柔道整復師養成施設の規制緩和をきっかけに、接骨院の数はこの20年で急増しました。2000年代初頭には約3万件だった施術所数は、2020年代に入ると5万件を超え、人口1万人あたり約4〜5院が存在するともいわれています。
とくに都市部では競合が密集し、1km圏内に複数の院が並ぶケースも珍しくありません。こうした状況から、立地だけでは差別化が難しい時代に突入しています。
市場は飽和?収益構造の変化と自費施術の比重
従来、接骨院・整体院の売上の大部分を占めていたのは、柔道整復療養費による保険収入でした。しかし、不正請求対策や審査厳格化により、保険適用の範囲が狭まり、療養費は減少傾向にあります。
このため、各院では「自費施術」への転換が急速に進み、現在は全体収入の2〜4割を自費メニューが占める院も増えています。骨盤矯正・姿勢改善・美容整体・EMSトレーニングなど、健康増進や美容を目的とした自由診療が支持を集めており、治療から予防・ケアへという発想転換が業界全体に広がっています。今後は、価格競争ではなくサービスの質・リピート率で収益を安定化させる経営が主流になる見込みです。
ニーズの変化:高齢化、健康志向、多様なサービスへのシフト
高齢化の進行とともに、「痛みを治す」だけでなく、再発予防や健康維持を目的とした利用が増えています。
特に40〜70代のシニア層では、リハビリ・ストレッチ・筋力維持を目的とするニーズが拡大。
また、若年層ではデスクワークやスマホ姿勢による不調対策、女性では美容整体など、多様な目的での利用が進んでいます。
こうした背景から、接骨院(整骨院)が「地域の健康インフラ」として果たす役割が広がっています。
市場縮小と競争激化が経営に与える影響
施設数の増加と人口減少により、1院あたりの患者数は年々減少傾向にあります。
2025年上半期には「マッサージ業・接骨院等」の倒産が過去20年で最多の55件に達し、その8割以上が「売上不振」を理由としていました。
このような環境では、保険依存型の経営モデルでは生き残りが難しく、
- 自費施術の導入による利益率の向上
- レセコンやCRM導入による業務効率化
- スタッフ教育と接遇品質の向上
などの取り組みが不可欠です。
また、経営者の高齢化による後継者不在問題も深刻化しており、近年ではM&Aによる第三者承継や大手グループへの統合が急増しています。
経営体力のある企業やグループが地域ネットワークを拡大する一方で、個人院は差別化と専門性を高める方向へ舵を切る動きが加速しています。
接骨院・整体院が抱える代表的な課題

接骨院・整体院業界は、高齢化による需要増がある一方で、供給過多・人材不足・後継者不在・制度厳格化といった課題が複雑に絡み合い、経営環境はかつてない厳しさを迎えています。ここでは、業界全体が直面する主な4つの課題を整理します。
後継者不在の深刻化:なぜ継がれないのか?
接骨院・整体院では、後継者問題が業界の構造的リスクになりつつあります。開業にあたっては国家資格である「柔道整復師」などの資格が必要であり、親族や従業員への承継が難しいという事情があります。その結果、「誰にも継がせられない」「継いでも経営が成り立たない」と判断して廃業するケースが増加しています。一方で、後継者を確保できない院がM&Aによる第三者承継を選ぶ動きも拡大しており、経営資源の維持・存続を目的とした譲渡が一般化しつつあります。
人材不足:採用難・定着難・育成リスク
接骨院業界は有資格者に依存する労働集約型ビジネスのため、人材確保が経営の生命線です。
しかし、施術所数が増加を続ける一方で、柔道整復師の国家試験合格者数は減少しており、採用競争が年々激化しています。さらに、労働環境の整備が不十分な院では、離職率の高さや育成の遅れが問題化することも。
小規模院では教育体制を整える余裕がなく、OJT中心で属人的な指導に頼るケースが多いため、若手が定着しにくい構造にならざるを得ません。
また、4院以上を展開する中規模グループでは、「採用ができない」「教育が追いつかない」といった人材マネジメント課題が顕在化しています。こうした背景から、近年ではM&Aによるスタッフごとの引継ぎで即戦力を確保するケースも増えています。
倒産や廃業の実態と主な要因
接骨院・整体院を含む「療術業」は、小規模経営による倒産・廃業リスクが高い業種です。帝国データバンクの統計によると、2018年には「マッサージ業・接骨院等」の倒産件数が93件に達し、過去10年間で最多を記録しました。
さらに、東京商工リサーチの調査(2025年7月発表)では、2025年上半期(1~6月)の「マッサージ業」倒産件数が55件にのぼり、過去20年間で最多水準を更新したことが報告されています。
倒産した院の9割以上が従業員5人未満の零細規模であり、主な原因は以下の通りです。
- 売上不振(競争激化・差別化不足)
- 資金繰り難(療養費入金までのタイムラグ、固定費負担)
- 制度改正への対応不足(療養費審査の厳格化による保険収入減)
とくに、保険診療だけに依存した経営は変化への対応が遅れやすく、自費診療の導入や経営効率化を怠った院ほど倒産リスクが高い傾向が顕著です。
経営の属人化と「1人院長モデル」の限界
多くの接骨院では、院長個人の技術や人柄、判断力に大きく依存する「属人経営」が続いています。こうした形態は、院長の存在がそのまま院のブランドや信頼の源泉となる一方で、経営拡大や事業継承を
しくする要因にもなっています。たとえば、院長が退いた途端に患者さまが離れるケースは少なくなく、実際にM&A後の運営に支障をきたす例も見られます。
また、院長一人が施術から経営、事務までを担う「1人院長モデル」は、生産性の面で限界が明確です。施術者1人あたりの月間売上は平均で約50万円前後とされ、労働時間が長くなりやすい構造的な課題を抱えています。こうした状況では、経営者自身が施術に追われ、戦略的な判断や事業拡大に十分な時間を割けません。
今後の接骨院・整体院の事業継承を見据えるうえでも、属人的な経営からの脱却は避けて通れません。受付や会計などを分業化し、マニュアルを整備することで、誰が担当しても一定の品質で運営できる体制を築く必要があります。院長の技術力だけに頼らず、スタッフが連携して院を支える「チーム経営」へと転換できるかが、今後の接骨院経営を左右する分岐点といえるでしょう。
なぜ今、事業継承が求められるのか

接骨院・整体院業界では、院長の高齢化や後継者不足が深刻化しており、事業継承の必要性が急速に高まっています。これまで個人経営が中心だった業界では、資格要件の厳しさや経営の属人化により、家族や従業員への承継が難しい状況が続いています。その一方で、廃業が増加すれば地域の医療・健康インフラが弱体化する懸念もあり、今や「事業を引き継ぐこと」は経営者個人の問題を超えて、地域全体の課題ともいえる段階に達しています。
院長の高齢化と引退の波
柔道整復師の平均年齢は年々上昇しており、現役の院長層にも引退を見据える動きが広がっています。体力的な負担や働き方の見直し、家族の事情などを理由に第一線から退こうとする経営者が増える中、資格を持つ後継者がいないために承継が難航するケースが多く見られます。特に、子ども世代が異業種に進む傾向が強まっており、「自分の代で終わらせるしかない」と考える院長も少なくありません。こうした状況は、今後の接骨院の事業継承を一層困難にし、廃業を加速させる要因になっています。早い段階から承継方針を定め、準備を進めることが重要です。
放置すれば「廃業」になってしまうリスク
後継者問題を先送りにした結果、事業を継続できず廃業を選ぶ院は少なくありません。廃業となれば、患者さまとの信頼関係や従業員の雇用、長年積み上げてきた施術ノウハウや地域での認知といった貴重な資産が失われます。特に接骨院は地域密着型の業態であるため、院の閉鎖は地域住民にとって「通える場所がなくなる」という深刻な問題につながります。事業継承を行うことで、こうした損失を回避し、培ってきた技術と信頼を次世代へ引き継ぐことができます。
雇用・患者・地域医療を守る視点からの継承の重要性
事業継承は、単に経営者が退くための手段ではなく、地域医療の継続を守るための重要な取り組みです。接骨院が廃業すれば、従業員の働く場所が失われ、通院していた患者さまの施術機会も途絶えます。反対に、第三者承継(M&A)などによって事業を引き継げば、雇用の維持とサービスの継続が可能になり、患者さまにとっても安心して通える環境を保つことができます。さらに、新しい経営体制が整うことで、設備投資やサービス品質の向上が進み、地域の健康支援拠点として発展する可能性も高まります。このように、接骨院の事業継承は、経営者自身の将来設計にとどまらず、雇用・患者・地域医療を守るうえで欠かせない社会的意義を持つ取り組みといえます。
事業継承へ
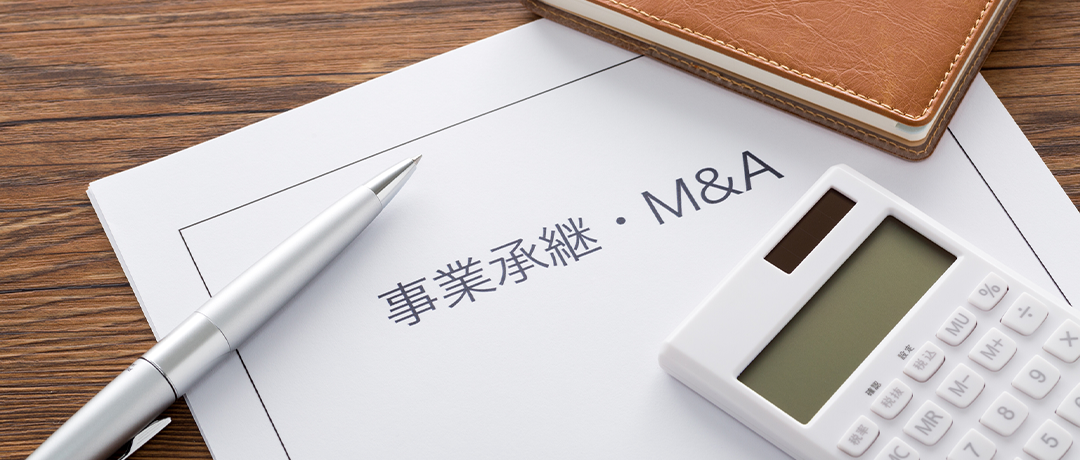
接骨院・整体院の事業継承には、主に「親族内承継」「従業員承継」「第三者承継(M&A)」の3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、経営者の年齢や家族構成、院の経営状況などによって最適な方法は異なります。承継は「引き渡す」だけでなく、「存続させる」ためのプロセス。早い段階から方向性を定めて準備を進めていきましょう。
【親族内承継】のポイント
もっとも一般的なのが、子どもや配偶者など親族への承継です。院の理念や経営方針を受け継ぎやすく、地域や患者さまからの信頼も維持しやすい一方で、柔道整復師などの国家資格が必要な点が大きなハードルとなります。後継者が資格を持たない場合は、養成校への進学や資格取得に数年を要するため、早期の準備が欠かせません。
また、家族間での資産や経営権の分配を巡るトラブルを防ぐため、税理士や専門家を交えて承継計画を立てることが重要です。
【従業員承継】のポイント
長年勤務してきたスタッフに承継するケースでは、院の運営方針や患者層を理解しているため、比較的スムーズな引継ぎが可能です。とくに、実務経験が豊富な施術管理者や副院長がいる場合は、経営の一部を段階的に任せながら承継を進める方法が有効です。ただし、経営責任や資金調達の負担が大きいため、後継者本人が経営に対する意識を持てるよう、早期から経営数値やノウハウを共有しておきましょう。承継資金は、金融機関の事業継承支援制度や日本政策金融公庫の融資制度を活用できる場合もあります。
【第三者承継(M&A)】のポイント
近年増えているのが、親族や従業員以外の第三者に譲渡する「M&Aによる承継」です。後継者がいない場合でも、経営資源を活かしたまま院を存続できる点が大きなメリットです。買い手は、同業の医療グループや介護・フィットネスなどの異業種企業が多く、資金力や運営ノウハウを持つケースが目立ちます。譲渡後も一定期間、院長が勤務を続ける「引継ぎ勤務型」も一般的で、従業員や患者さまが安心して通える環境を維持できます。専門の仲介会社を通じて条件交渉や契約手続きを行えば、適正な評価での譲渡が実現しやすくなります。
どの方法が適している?判断基準の整理
どの承継方法が最適かは、後継者候補の有無・経営規模・譲渡後の関与意向によって変わります。家族経営を守りたいのか、従業員の雇用を優先したいのか、あるいは院のブランドを残したいのか。まずは目的を明確にしましょう。いずれの方法を選ぶ場合でも、承継計画は少なくとも3〜5年前からの準備が理想とされます。事業や財務の整理、人材育成、信頼関係の引継ぎなどを段階的に進めることで、承継を円滑に行い、安定した経営の継続へとつなげることができます。
接骨院・整体院におけるM&Aの実情
小規模事業でも買い手は見つかるのか?
結論から言えば、1~3店舗規模の接骨院・整体院でも買い手が見つかる可能性は十分にあります。 大手グループや異業種企業にとって、地域密着で患者さまとの信頼を築いている院は、既存顧客をそのまま引き継げる魅力的な資産です。とくに、柔道整復師など有資格者が在籍している場合は、人材確保の観点からも評価が高くなります。さらに、自費診療の割合が高く、安定した収益を維持している院は、経営の再現性が高いと判断されやすいため、より高い条件での売却が期待できます。
異業種参入が進む背景
M&Aの増加を支えているもう一つの要因が、介護・医療・フィットネス業界など異業種からの参入です。 これらの企業は、接骨院・整体院が持つ「身体機能の改善・予防医療」のノウハウを自社サービスに組み込み、リハビリ・ヘルスケア・ボディメンテナンスなど新たな収益源を確立しようとしています。たとえば、介護施設がリハビリ要素を強化したり、スポーツジムがボディケア部門を併設するケースが代表的です。こうした異業種との連携により、既存院にとっても患者層の拡大や経営基盤の強化といったシナジー効果が生まれています。
実際に行われているM&Aの規模・動機・流れ
接骨院・整体院のM&Aは、事業譲渡形式による1〜3院の小規模案件が中心です。買い手側の動機は、有資格者の確保や新エリアへの進出、ブランドの強化などが多く見られます。 譲渡までの流れとしては、まず専門の仲介会社やM&Aプラットフォームに相談し、院の財務状況・契約条件・従業員体制を整理。その後、交渉・デューデリジェンス(買収監査)を経て、譲渡契約が締結されます。一般的には相談から成約まで半年〜1年程度を要し、譲渡後もしばらくは院長が残って引き継ぎを行うケースが多くなっています。
成功事例と失敗事例から学ぶポイント
成功するM&Aの共通点は、「早期準備」と「経営の透明性」です。
たとえば、自費診療を軸に高収益を実現していた院では、リピート率や顧客満足度を数値化し、経営データを整理していたことで高い評価を受けました。逆に、保険請求の不備や帳簿の不透明さがある場合は、デューデリジェンス(買収監査)で減額・破談に至るリスクが高くなります。
また、買収後の経営方針が急に変わると、患者さま離れやスタッフの退職につながることもあります。M&Aを成功させるためには、「数字の整理」だけでなく、「人と信頼の引き継ぎ」を重視する姿勢が欠かせません。
M&Aを成功させるためのポイント

接骨院・整体院のM&Aを成功させるには、単に高く売却することを目的にするのではなく、事業の魅力を正確に伝え、引き継いだ後も安定して運営できる状態を整えることが重要です。買い手が安心して判断できるよう、経営の中身や人材体制、仕組みを整理し、分かりやすく示す準備を進めましょう。
院の魅力を「見える化」する準備
自院の価値を正しく伝えるためには、数字と実績をもとにした信頼性のある情報整理が必要です。まず、売上や費用、利益の推移をまとめておくことで、経営の安定性を具体的に示せます。あわせて、リピート率や来院頻度、患者さまの年齢層といったデータも整理し、地域でどのように信頼を得てきたかを明らかにしておきましょう。
また、保険請求が適正に行われているか、設備や機器がきちんと整備されているかも重要な確認項目です。資産と経営の線引きを明確にし、健全な運営体制を示すことで、買い手が検討しやすくなります。
スタッフ・患者さまへの影響を抑える
M&Aでは、従業員や患者さまの不安をできるだけ減らすことが求められます。スタッフには、待遇や勤務条件の変化を早めに説明し、安心して働ける環境を整えることが大切です。資格取得や研修の機会を設けておくと、今後の成長にもつながります。患者さまには、担当施術者やサービス内容をできる限り維持し、これまでと同じように通える環境を保つことが重要です。引き継ぎ期間中に経営者が残ってサポートする体制を取ると、移行がよりスムーズになります。
秘密保持・法的手続きの整備
M&Aを安全に進めるためには、情報管理と契約準備を慎重に行う必要があります。買い手候補と交渉を始める際は、まず秘密保持契約(NDA)を結び、関係者以外に情報が漏れないよう管理します。従業員や取引先に知らせる時期も慎重に判断することが求められます。
また、契約内容には競業避止義務などの制限が含まれることがあるため、M&Aの実務経験を持つ弁護士や会計士、アドバイザーの助言を受けながら進めることが望ましいです。
買い手を選ぶ際に確認すべき点
M&Aを成立させるうえで最も重要なのは、理念や運営方針の一致です。面談では、買い手の経営方針や従業員への考え方を確認し、自院の運営方針と合うかどうかを見極めます。理念が異なる相手に譲渡すると、運営の継続が難しくなる場合があるからです。
また、買い手が持つ教育体制や管理システム、DX化の仕組みなどを把握し、従業員が働きやすい環境が維持できるかを確認しておくと安心です。将来的な拡張計画やサービス展開の方針まで理解したうえで契約すれば、引き継ぎ後の混乱を防ぎやすくなります。
事業継承を進める際の注意点とリスク

接骨院・整体院の事業継承では、一般企業とは異なり、資格や許認可の継承、名義変更の手続き、人材面のリスクなど、業界特有の課題が発生します。
行政上の届出や契約関係の処理を誤ると、引き継ぎ後に営業を続けられなくなる可能性もあるため注意が必要です。
許認可・施術管理者に関する手続き
接骨院・整体院を継続して運営するには、柔道整復師などの国家資格を持つ施術管理者を配置することが前提です。
後継者が資格を持たない場合は、有資格者を管理者として任命するなどの体制づくりが必要になります。
また、事業譲渡によって承継を行う場合には、保健所への施術所開設届や療養費受領委任契約の変更申請など、行政上の手続きを確実に行わなければなりません。これらを怠ると営業停止になるおそれがあるため、事前に行政機関への確認を済ませておくことが重要です。
賃貸契約・保険制度の名義変更
院を賃貸物件で運営している場合は、賃貸借契約やリース契約の名義変更、保証人の変更などが必要になります。契約書に「支配権移転(チェンジ・オブ・コントロール)」条項が含まれている場合、貸主への事前承諾が求められることもあります。
また、柔道整復療養費の受領委任契約については、支払い先が施術管理者単位で管理されているため、新たな施術管理者名義への変更を行う必要があります。こうした手続きを引き継ぎ前に整理しておくことで、承継後の運営を安定させることができます。
競業避止義務など契約上の確認
M&A契約では、譲渡後に同一地域で類似事業を開業できないよう制限を設ける競業避止義務が定められる場合があります。期間や地域の範囲によっては、売却後の活動に制約が生じるため、契約締結前に内容を十分に確認しておくことが大切です。
また、報酬を継続的に得るテール条項など、契約後の条件も含めて整理しておくと、将来的なトラブルを防ぎやすくなります。
従業員の退職リスクへの配慮
接骨院・整体院は、施術者やスタッフの信頼関係に基づいて成り立つ事業です。事業継承やM&Aによって経営方針や体制が変わると、従業員が不安を感じて離職するケースも。買い手は、待遇や雇用条件の変更内容を明確に伝え、スタッフが安心して働ける環境を整えることが求められます。さらに、未払い残業代などの簿外債務がある場合、承継後に問題化することがあります。事前に財務・法務のデューデリジェンスを行い、債務状況を明確にしておきましょう。
また、オーナー交代によって患者さまが離れるリスクもあるため、引き継ぎ期間中に現経営者が一定期間残り、患者対応を継続する形が効果的です。
まとめ
事業継承を考えることは、経営を終える準備ではなく、これまで積み重ねてきた努力と信頼を次へつなぐための前向きな判断です。
「まだ早い」と感じているうちに、制度の変更や人材の入れ替わりなど、環境が大きく変わることも少なくありません。
早い段階から準備を始めておくことで、想定外のトラブルを防ぎ、納得のいく形で次の経営者へ引き継ぐことができます。
承継の方法や進め方には正解があるわけではありませんが、信頼できる専門家に相談することで、最適な選択肢を明確にしやすくなります。
現状の整理から引継ぎの計画づくりまで、第三者の視点を交えて進めることが、後悔のない承継につながります。
事業の将来に少しでも不安を感じている方は、まずは一度ご相談ください。
私たちは、接骨院・整体院の現場を理解した専門家として、経営者の思いを尊重しながら、円滑な承継の実現をサポートいたします。