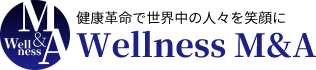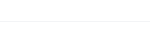接骨院経営が厳しい理由
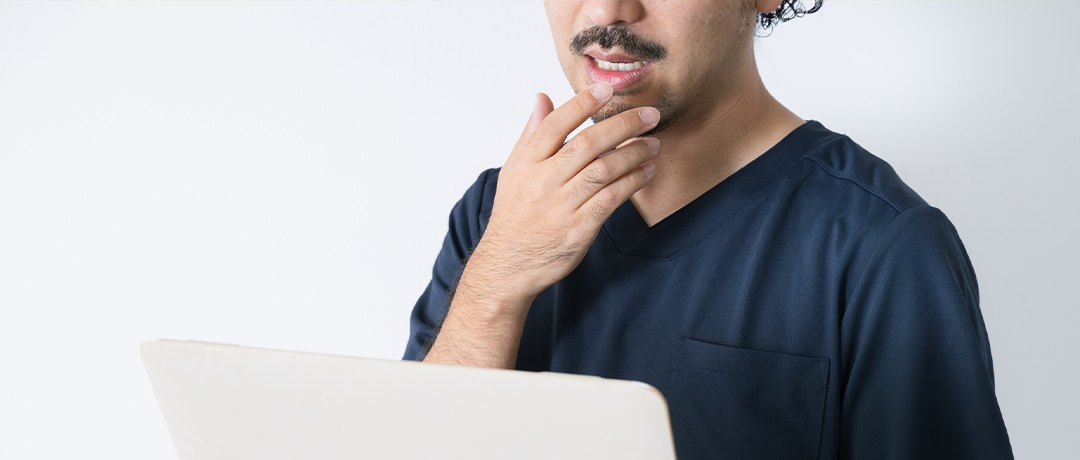
競争の激化と差別化の難しさ
全国の接骨院・整体院の数はこの10年で大幅に増え、競争は年々厳しさを増しています。
一方で、患者数の伸びは横ばいのままで、地域によっては需要を上回る数の院が開業しています。この供給過多により、集客の難易度が上がり、売上が安定しない院も少なくありません。
実際に、東京商工リサーチの調査では、接骨院やマッサージ業を含む「療術業」の倒産・廃業件数が増加傾向にあり、2025年上半期には過去20年で最多を更新しています。
競争の中で差別化できず、経営を続けられなくなる院が増えているのが現状です。
来院理由が「近いから」「料金が安いから」だけでは、患者の定着にはつながりません。
技術力や接客、院内の雰囲気といった体験価値をどう高めるかが、今後の安定経営を左右します。
保険請求の厳格化による収益低下
柔道整復師による保険請求は、かつて安定収益の柱とされてきました。
しかし近年は審査が厳しくなり、支給対象も限定されつつあります。その結果、保険収入が減少し、自費施術の導入を余儀なくされる院が増えています。
自費施術への転換は利益率を高める手段ですが、価格設定や集客の設計が不十分だと、かえって経営が不安定になる場合もあります。
保険制度に頼らない経営を確立するには、患者に納得してもらえる根拠を持つことが欠かせません。説明の丁寧さや提案力が問われる時代になっています。
人材確保の難しさと属人化のリスク
柔道整復師の高齢化や離職率の高さも、経営を圧迫する要因です。スタッフを採用しても定着しない、院長ひとりに負担が集中するなど、このような状況では、業務が属人化し、長期的な経営基盤が弱まります。
属人的な経営は、施術の品質や接客のばらつきを生み、患者満足度の低下にもつながります。継続的な運営を考えるうえで、スタッフ教育や業務分担の仕組み化は避けて通れません。
経営が厳しくなる接骨院の共通点

集客導線の設計が不十分
広告やSNSを活用していても、ターゲット層や訴求内容が明確でないケースが多く見られます。「誰に、どんな施術を、どの価格帯で提供するのか」を整理しないまま発信しても、成果は上がりません。
口コミや紹介に頼るだけでは、来院数の波が大きく、経営が安定しにくくなります。また、予約システムやLINE公式アカウントを導入していても、運用が形骸化していることもあります。
導線を可視化し、集客から予約、再来院までの流れを管理することが重要です。
経営数値やノウハウを把握していない
経営不振に陥る院の多くは、数字の把握が不十分です。売上、利益、広告費、人件費といった基本的な項目を定期的に確認しなければ、改善の方向が見えません。
さらに、施術のスキルはあっても、経営に関する知識やノウハウを学んでいないケースが多く見られます。利益構造を理解せずに料金設定を行えば、施術数が増えても利益が残らないという事態に陥ります。
経営の数字を「管理」ではなく「判断の材料」として使う意識が必要です。
患者満足度を計測していない
技術だけではリピートは生まれません。
施術の質、接客、通いやすさなど、患者が感じる価値を定期的に把握することが必要です。
口コミアンケートやLINEでのフォローアップなど、小さな仕組みを積み重ねることで、離脱を防ぎやすくなります。
施術技術の幅が狭い
患者の症状や目的が多様化する中で、限られた施術しか提供できない院はリピートにつなげにくくなっています。保険適用の施術だけでなく、自費メニューやリハビリ、ストレッチなど複数のニーズに応えられる柔軟性が求められます。
新しい技術や機器を導入し、施術の幅を広げることが、結果的に集客と収益の安定化につながります。
経営を立て直すための具体策

自費施術メニューの強化
保険収益が減少する中で、自費施術の導入は避けられません。骨盤矯正や姿勢改善、筋膜リリースなど、専門性を打ち出したメニューを導入し、単価と満足度を高めることが重要です。
ただし、価格を上げるだけでは通院継続にはつながりません。カウンセリングで悩みを可視化し、課題解決の流れを説明するなど、納得感のある提案が必要です。
価格よりも「価値」で判断される仕組みづくりが求められます。
デジタル集客の最適化
GoogleビジネスプロフィールやLINE公式アカウントの活用は、地域集客に欠かせません。
特にスマートフォン検索での露出強化は、費用対効果が高い施策のひとつです。
「接骨院 地域名」などの検索結果で上位表示されるよう、口コミ対応や情報更新を継続的に行いましょう。
また、来院後のコミュニケーション設計も重要です。
LINEでの次回予約リマインドや再来院キャンペーンなど、患者との接点を維持することでリピート率を高められます。
スタッフ教育と業務の仕組み化
院長一人に依存しない運営体制を築くことが、持続的な経営の前提です。
受付、会計、予約管理などをマニュアル化し、誰が担当しても一定の品質を保てる仕組みを整えましょう。
また、スタッフに裁量を与え、意見を反映できる環境をつくることで、定着率も向上します。
チーム全体で経営を支える体制が整えば、院の信頼性も高まります。
経営に行き詰まったときの対応策
経営コンサルティングの活用
経営が思うように安定しないときは、第三者の視点で現状を整理することが効果的です。接骨院の経営に詳しいコンサルタントに相談すれば、売上や集客、人材など複数の課題を客観的に分析し、改善の優先順位を明確にできます。多くの院では「人が来ない」「利益が残らない」といった問題の背景に、価格設定や導線設計の甘さがあります。コンサルティングでは、広告費の最適化や再来院率を高める仕組み化など、実務に即した改善が可能です。感覚ではなくデータに基づいた判断を身につけることで、経営の安定と再成長が見込めます。
事業譲渡・M&Aによる再出発
経営の立て直しが難しい場合は、事業を譲り渡す方法もあります。M&Aを活用すれば、培ってきた技術や信頼を新しい経営者に引き継ぎながら、スタッフや患者の環境を守ることができます。
介護・フィットネス業界など、異業種からの参入が進む今、承継後に安定した運営を実現するケースも増えています。契約には法的手続きが伴うため、弁護士や会計士など専門家と連携し、条件を丁寧に確認することが重要です。M&Aは経営を手放す行為ではなく、院の価値を次世代へ残す前向きな選択といえます。
接骨院の経営を守るために、早めの行動を
接骨院を取り巻く経営環境は厳しくなっていますが、課題を正しく把握し、改善策を実行すれば再建は十分に可能です。
現状の延長ではなく、仕組みを整えることで、持続的な成長が見込めます。
私たちは、接骨院・整体院の経営支援と事業承継に特化したサポートを行っています。
経営分析から改善計画の立案、譲渡を含む将来設計まで、一つひとつの状況に合わせて具体的にご案内します。
「このままでは続けられない」「何から始めればいいのか分からない」と感じたときは、ぜひご相談ください。
課題を整理することで、次に進む方向が見えてきます。
接骨院の価値を守り、地域に必要とされる院として再び歩み出せるよう、全力で支援いたします。