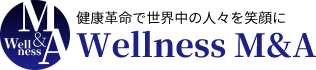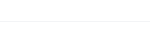01接骨院・整体院M&Aが注目される背景と業界動向

近年、接骨院や整体院におけるM&A(売却・事業承継・譲渡)の動きが加速しています。その背景には、業界全体が直面する構造的な課題と、経営環境の変化があります。
まず、深刻化しているのが経営者の高齢化と後継者不在です。かつては家族間での承継が一般的でしたが、近年では「身内に継がせない」「そもそも後継者がいない」といったケースが増加しており、第三者への事業承継を現実的な選択肢とする経営者が増えています。
また、集客や人材確保の難しさといった経営課題も複雑化しています。院長一人に依存した属人的な運営では限界が見え始めており、Web集客、採用・教育、制度対応、財務管理など、多面的な経営力が求められる時代に移行しつつあります。
こうしたなか、グループ院や法人による買収ニーズも年々高まっている状況です。複数店舗を一括管理し、サービスの標準化や人材の流動性を確保する経営モデルは今後ますます主流になっていくでしょう。
個人経営者にとっても、M&Aを通じてグループの一員となることで、経営負担の軽減や安定的な運営環境の確保が可能となります。
これまでのように、すべてを一人で抱えて経営していく時代から、「個人開業からグループ運営へ」という流れが加速している今、M&Aは院の未来を守るための有効な選択肢となりつつあります。
整骨院の急増と過剰供給による競争激化
1998年の規制緩和以降、柔道整復師の養成施設が急増し、それに伴い整骨院の開業数も大きく伸びました。2020年時点で施術所は5万件を超え、業界は供給過多の状態に。新規参入が相次いだ結果、同業間での競争が激化し、多くの整骨院が収益確保の難しさに直面しています。
不正請求問題と制度改正による経営圧迫
整骨院業界では、受領委任制度の運用を背景に療養費の不正請求が社会問題化しました。これにより、国は保険請求ルールの厳格化や罰則強化に踏み切っており、まじめに運営する院にとっても請求手続きの負担増・コスト増が経営を圧迫する要因となっています。さらに、少子高齢化を背景に、社会保障費の適正化(削減)政策も進行し、療養費収入の減少に拍車をかけています。
市場は停滞傾向、競争激化により経営リスクも増加
接骨院や鍼灸院、マッサージ院は、いずれも国家資格者による医療類似サービスとして位置づけられており、整形外科や民間資格サロンなど周辺業種とは提供体制や法的位置付けが異なります。しかし、近年はこうした周辺業種との顧客獲得競争が激化しており、従来のビジネスモデルだけでは安定経営が難しくなりつつあります。
実際、2022年の柔道整復・鍼灸・マッサージ市場全体の規模は前年比98.8%の9,560億円とわずかに減少。接骨院(柔道整復)分野の停滞が影響しています。2023年はコロナ収束後の来院回復により前年比103.0%の9,850億円まで持ち直しましたが、依然として成長余地は限定的です。
また、競合院の乱立や人材不足、広告規制強化なども経営環境を圧迫しており、特に従来型の院経営に依存している事業者は淘汰のリスクに直面しています。整骨院・療術・マッサージ業者の倒産件数も増加傾向にあり、市場の再編が進むなかで、収益構造の見直しや差別化戦略が急務となっています。
保険外施術へのシフトと競合拡大
競争環境が厳しくなるなか、多くの整骨院が慢性症状への対応や自由診療へとサービスの重心を移しつつあります。
ただし、こうした分野では、整体院・カイロプラクティック・マッサージ店など異業種との競争も激化しており、従来の保険診療だけに頼らない経営戦略が求められています。
デジタル集客と多角化戦略の重要性
集客手段も変化しています。WebサイトやSNS、スマートフォンアプリなどを活用したデジタルマーケティングの活用が必須となりつつあります。一方で、高齢者層への訴求にはチラシやポスティングといった従来型の手法も依然有効です。また、一部の整骨院では、スポーツトレーナーや介護分野への進出といった事業の多角化にも取り組むなど、新たな収益モデルの構築が進められています。
後継者動向調査から見える課題と変化
帝国データバンクが2024年に実施した全国・全業種約27万社を対象とする調査によると、後継者が「いない」「未定」と回答した企業は52.1%にのぼり、なお半数を超える企業で事業承継の課題が残っていることが明らかになりました。
一方で、相談窓口の整備や支援制度の拡充などにより、後継者不在率は7年連続で改善。ただし、その改善ペースは鈍化傾向にあり、経営環境の変化や後継者辞退などにより承継が中断・頓挫するケースも増加しています。
とくに「50代・60代」の現経営者で後継者不在率が悪化しており、高齢化が進む中で事業承継のタイミングを逃すリスクが顕在化しています。こうした背景もあり、第三者への承継=M&Aを選ぶ企業が増えているのが現在の流れです。
02接骨院・整体院の開業が失敗する6つの理由

整骨院・接骨院の開業には多くの夢と期待が込められていますが、実態は厳しいものです。整体業界の廃業率は95%以上とも言われ、開業後も継続的に経営できている院はごく一部にとどまります。理想だけでは乗り越えられない現実的な経営判断が求められます。東京商工リサーチのデータによると、2018年における「マッサージ業、接骨院等」の倒産件数は過去10年で最多となる93件にのぼりました。競争激化や収益性の低下に加え、広告規制や制度改正も影響しており、今後も油断できない状況が続きます。
失敗の理由 1競合の増加
整骨院・接骨院業界はここ数年で急速に店舗数が増え、特に都市部ではすでに飽和状態に近づいています。人口の集中するエリアでは、数百メートル圏内に複数の院が並ぶケースも珍しくありません。
こうした状況では、開業直後から集客競争に巻き込まれることになり、広告費や販促コストがかさむ一方で、思うように来院数を確保できないケースも少なくありません。競合との差別化を図らずに出店してしまうと、集客に苦戦し、開業後すぐに経営が行き詰まるリスクが高まります。
開業前には、エリアの競合状況や人口動態を把握し、ポジショニングの明確化とサービスの差別化戦略が不可欠です。
失敗の理由 2立地・物件選びの失敗
接骨院・整体院の開業において、立地選びは集客の成否を左右する最重要ポイントです。人通りが多く、視認性が高く、通いやすい場所であることが、新規顧客の獲得には欠かせません。
しかし、家賃を抑える目的でアクセスが悪い・目立たない物件を選んでしまうと、せっかくの技術やサービスも利用される機会が減り、経営を圧迫する原因になります。とくに2階以上や裏通りの立地は要注意です。
また、すでに競合が密集している地域に安易に出店するのもリスクが高く、エリア特性や人口動態を踏まえた事前の市場調査が欠かせません。立地の選定ミスは、開業後に取り返しがつきにくいため、慎重な判断が求められます。
失敗の理由 3初期費用・運転資金の不足
接骨院・整体院の開業では、物件取得費・内装費・機材費など初期費用がかさみがちです。とくに「立地や設備にこだわりすぎた結果、予定を超える投資をしてしまう」というケースは少なくありません。
この段階で予算を使い切ってしまうと、開業後の運営資金が不足し、資金繰りの悪化につながる恐れがあります。
また、開業直後はすぐに黒字化できるとは限らないため、家賃・人件費・広告費などの固定費をカバーする運転資金の確保も非常に重要です。
十分な資金計画がないままスタートすると、集客の成果が出る前に資金が尽きてしまい、経営が立ち行かなくなるリスクが高まります。初期投資と運転資金のバランスを見極めた慎重な準備が欠かせません。
失敗の理由 4集客ができない
開業後に直面する最大の壁が「集客」です。とくに知名度がないうちは、どれだけ技術やサービスに自信があっても、患者が来院しなければ経営は成り立ちません。競合が多い地域ではなおさら、選ばれる理由を明確に打ち出す必要があります。
にもかかわらず、地域に根ざした宣伝活動やデジタルマーケティングが不十分な院が多く、集客に苦戦するケースが目立ちます。
ホームページやSNS、口コミサイトの活用、地域のイベント参加など、多角的な認知獲得施策を講じることが重要です。
また、既存顧客からの紹介を促す仕組みも、安定した集客力を築くうえで欠かせません。開業後のスタートダッシュを支えるのは、「集客戦略の質と量」にかかっています。
失敗の理由 5ターゲット設定の不足
接骨院・整体院の開業において、「誰に向けた施術なのか」を明確にしないままスタートするのは大きなリスクです。地域の年齢層やライフスタイルを踏まえず、幅広く対応しようとすると、結果的にどの層にも響かないサービスになりがちです。
たとえば、高齢者の多い地域で若年層向けの姿勢改善プログラムを中心に据えても、需要とのミスマッチで集客は難しくなります。患者の課題に応じたメニューや接客を設計しないと、リピートや紹介にはつながりません。
開業前に地域分析とペルソナ設定をしっかり行い、「誰のための院なのか」を明文化することが、差別化と安定経営のカギとなります。
失敗の理由 6サービスの低下
接骨院・整体院は「治療の場」であると同時に、「サービスを提供する場」でもあります。どれほど高い技術があっても、接遇や院内環境に配慮がなければ患者の満足度は得られません。
たとえば、受付の対応が雑だったり、施術室が清潔でなかったり、待ち時間が長いまま放置されていたりするだけで、来院者の印象は大きく損なわれます。サービス品質の低下はリピート率の低下や口コミでの評価悪化につながり、経営を圧迫する要因になり得ます。
「患者目線での快適さ」や「心配り」が、地域で選ばれる院づくりの土台となる点を忘れてはいけません。
03開業リスクを避ける手段としてM&A・事業譲渡が注目

前述したように接骨院・整体院の開業には数多くの課題が伴い、特に新規参入では成功までのハードルが高くなりがちです。しかし、その開業リスクを避ける手段としてニーズが高まっているのがM&Aです。以下に、それぞれの課題に対してM&Aがどのようにリスクを軽減できるかをご紹介します。
注目のポイント
POINT 01競争に埋もれない「地域での実績」を引き継げる
新規開業では、すでに競合が密集している地域での集客に苦戦するケースが多くあります。M&Aなら、地域内で一定の認知度や信頼を持つ院を引き継げるため、スタート時から競合に埋もれにくい状態で事業を始めることが可能です。
POINT 02すでに集客実績のある「勝ちパターンの立地」から始められる
成功する立地選びは非常に難しく、開業後に「場所の失敗」に気づくことも。M&Aであれば、すでに実績のある立地や物件をそのまま引き継げるため、失敗リスクを大幅に軽減できます。
POINT 03開業時の高額な初期投資を抑えられる
ゼロから開業する場合、設備投資・内装工事・広告費などで多額の費用が発生します。一方でM&Aなら、既存の施設や設備、スタッフ体制をそのまま活用できるため、初期費用を抑えてスタートできます。
POINT 04既存の患者さまをそのまま引き継げる
開業初期に最も苦労するのが「集客」です。M&Aではすでに通院している患者さまがいる状態で始められるため、売上のベースが見込めるだけでなく、信頼関係の維持にもつながります。
POINT 05スタッフと接客品質をそのまま承継
サービスの質はリピート率に直結します。M&Aでは、すでに接客・運営スキルが備わったスタッフを含めて承継できるため、サービス品質を安定的に維持しやすく、スムーズな運営が可能です。
04接骨院・整体院を売却・M&Aを活用するメリットとは

売却・M&Aのメリット
MERIT 01大手グループに入ることで経営の安定と事業拡大が図れる
豊富な資本力や運営ノウハウを持つ企業グループに参画することで、財務面・集客面の両方で支援を受けられるのが大きな魅力です。グループのブランド力や知名度を活かし、患者数の増加やサービスメニューの拡充も見込めます。
売却後の運営形態は多様で、既存ブランドをそのまま残しながら子会社として展開するケースもあれば、グループブランドに切り替えて運営するパターンもあります。介護・リラクゼーション・フィットネスなど隣接業種への譲渡も増えており、異業種連携による成長戦略の一環としてM&Aを活用する動きが広がっています。
売却後も経営に携わりたい方は、グループ内で店長や役員として引き続き関わることも可能です。
MERIT 02まとまった資金を確保できる
接骨院・整体院の売却を通じて、経営者は一度にまとまった現金を得ることが可能になります。黒字経営の院であれば、安定した収益性や地域での認知度、スタッフの継続雇用といった要素が高く評価され、希望に近い金額での売却が実現するケースも少なくありません。
また、経営が厳しい状況でも、立地や設備、人材といった「経営資源」に価値を見出す買い手が現れることもあります。こうした資金は新たな挑戦のための原資として使えるほか、引退後の生活資金としても役立ちます。
さらに、複数店舗を経営している場合には、一部店舗のみを売却して資金を確保することで本業への集中や事業再編成にもつなげられます。
MERIT 03閉院時に発生するコストを削減できる
接骨院・整体院を閉院する場合、原状回復費用や解約までの家賃、設備の処分費用など、思いのほか多くのコストが発生します。特に賃貸物件の場合は、原状回復のための内装解体費や、契約上の予告期間中に発生する家賃が経営者の大きな負担となりがちです。
しかし、M&Aを活用して現状のまま譲渡できれば、こうした退店コストの多くを回避できます。買い手が現在の設備や立地に価値を見出した場合は、原状回復なしで引き継ぐことが可能ですし、条件が整えば賃貸契約の引継ぎもスムーズに行えます。
事業を閉じるよりも、売却という選択をすることで、経営者自身の負担を大きく軽減できる点は見逃せません。
MERIT 04後継者不在でも事業承継が実現する
家族や従業員に後を託せず、将来の事業継続に不安を抱える接骨院・整体院の経営者は少なくありません。こうした「後継者不在」の課題に対して、M&Aという選択肢は有効な解決策となります。
第三者への譲渡を通じて、現在の院をそのままの形で次世代へ引き継ぐことができるため、患者さまや従業員に与える影響も最小限に抑えられます。最近では、同業他社や周辺サービス業などによる買収ニーズも高まり、後継者に悩む経営者にとって、事業承継の現実的な手段としてM&Aの活用が広く受け入れられつつあります。
MERIT 05従業員や患者さまを引き継げる
廃業や閉院によって、長年勤めてくれた従業員の雇用や、通い続けてくれた患者さまの治療継続が断たれてしまうことは、経営者にとって大きな心残りになり得ます。
しかし、M&Aによって院そのものを引き継ぐ形で売却すれば、スタッフの雇用を維持したまま、新たな運営体制へとスムーズに移行できます。また、患者さまのデータや診療方針なども適切に引き継ぐことで、通院環境やサービス品質を守ることが可能です。
地域に根ざした医療サービスを絶やさず、関係者すべてにとって円満な事業承継を実現する手段として、M&Aは大きな意義を持っています。
05接骨院・整体院M&Aの相場と価格の目安

接骨院・整体院を売却する際、気になるのが「いくらで売れるのか」という点です。売却価格は一律ではなく、個々の院の収益性や立地、設備、人材などさまざまな要素に基づいて決まります。
年買法(年倍法)による簡易的な評価が一般的
中小規模の整骨院・整体院では、「年買法(年倍法)」というシンプルな手法で企業価値を見積もるのが一般的です。
この手法では、直近の利益や平均利益に一定の年数(倍率)を掛け合わせて、今後得られるであろう利益をざっくり評価します。そこに、帳簿上ではなく「時価で評価し直した純資産」を加えた合計が、おおよその企業価値とされます。
ただし、利益がほぼ出ていない赤字状態の院でも立地・設備・人材などの経営資源に価値があると判断されれば一定の価格がつくケースもあります。
売却価格に影響する主なポイント
実際の評価額(利益に掛ける年数)や売却価格には、以下のような要素が影響します。
- 利益の水準と安定性
- 立地の良さ(駅近・住宅街など)
- 院内の設備・内装の状態
- スタッフの質と在籍状況
- 患者数・カルテの数
- 店舗賃料と契約条件
- 現在の経営者が残るかどうか(引継ぎやすさ)
- 解約予告の有無(すでに通知済みかどうか)
たとえば、現院長が引退予定で集客が経営者個人に依存している場合、事業引継ぎが難しいとみなされて評価額が下がる可能性があります。逆に、院長が一定期間残ってサポートする契約がある場合は、価値を維持しやすくなります。
相場は200万〜1,000万円前後、条件次第で高額にも
整骨院・整体院の売却価格は、一般的に営業利益の2〜3年分が目安とされており、金額にすると200万〜1,000万円前後で取引されるケースが多くなっています。ただし、立地・既存患者数・設備の状態・スタッフ構成などによって大きく変動し、条件が整っている院であれば2,000万円以上の評価がつくこともあります。
一方、収益性が低い店舗や設備が古い場合などは、数十万円〜300万円程度にとどまるケースもあります。
特に複数店舗を展開するグループ院や、M&Aにより大手のチェーンに統合されるような案件では、売却価格が1億円超となる例もあり、事業規模や内容に応じて幅広い価格帯が存在します。
| 規模・条件 | 売却価格相場 | |
|---|---|---|
| 一般的な個人院(1店舗) | 200~1,000万円前後 | ※営業利益や立地で幅広く変動 |
| 好立地・収益安定の個人院 | ~2,000万円以上 | ※店舗設備、患者数、スタッフ状況次第 |
| 複数店舗のグループ・大規模案件 | 2,000万円~1億円超 | |
| 設備や利益に難のある店舗 | 数十万円~300万円ほど | |
事例01個人経営の接骨院を地元法人が買収
- 売却理由
- 院長の引退および後継者不在
- 譲渡内容
- 院の設備・スタッフ・顧客・診療体制をそのまま承継
- 買収側
- 地元の整形外科グループ
20年以上地域に根差した接骨院を運営していた院長が、高齢に伴い引退を決意。身内に後継者がいないため、信頼できる相手に院を引き継ぎたいという思いから、M&Aを選択しました。
譲渡先は同じ地域で整形外科を展開している医療法人で、既存の治療内容・スタッフ体制を維持することを条件に買収が成立。売却後も院の看板や名称はそのまま継続され、スタッフも雇用を維持。引き継ぎ期間中は院長も一定期間サポートし、地域患者の混乱を避けながらスムーズな承継が実現しました。
事例02整体院を法人が買収し、フランチャイズ展開へ
- 売却理由
- オーナーのライフスタイル変化(育児との両立)
- 譲渡内容
- 店舗運営・スタッフ・顧客データ・ブランド資産
- 買収側
- 健康・美容関連事業を展開する法人企業
都心駅近に店舗を構える人気整体院を経営していたオーナーが、育児との両立を優先するために現場から退きたいと希望。院の収益性・集客力・スタッフ対応力が評価され、健康関連事業を拡大中の法人が買収を決定しました。
買収後はブランドを法人側のフランチャイズ名に変更し、価格やサービス内容を他店舗と統一。既存顧客には引き継ぎの説明とフォローを丁寧に行い、信頼を損なうことなく再スタート。結果として新規顧客の流入と既存リピーターの維持に成功し、同モデルでの他店舗展開にもつながりました。
06売却価格を高めるポイント

M&Aや事業譲渡においては、「いかに買い手にとって魅力的な資産であるか」を客観的に示すことが、売却価格の上昇につながります。単に院を売るのではなく、「事業としての価値」を整理・可視化し、交渉材料として提示できるかどうかが成否を分けます。以下は、売却価格を引き上げるうえで意識したい4つの具体的なポイントです。
売却査定のポイント
POINT 01院の魅力を数値で「見える化」する
「売上が安定している」「患者が多い」などの主観的な表現だけでは買い手に伝わりません。月次売上や利益率、患者数の推移、リピート率、来院経路の内訳など、定量的なデータで院の強みを「見える化」することで、説得力が大きく向上します。とくに、新規・既存の来院割合や平均単価などは評価の鍵になります。
POINT 02財務書類・契約関係の整理と開示準備
損益計算書や貸借対照表などの財務書類に加え、賃貸借契約やリース契約、スタッフの雇用契約など、事業運営に関わる書類を事前に整理しておくことが重要です。これにより、買い手が事業全体のリスクや継続性を評価しやすくなり、価格交渉でも優位に立てます。透明性の高さは信頼の獲得にも直結します。
POINT 03属人化の解消(スタッフへの業務分散)
「院長がいなくなったら成り立たない」と見なされると、買い手は将来の安定性に不安を抱きます。特定の人物への依存度を下げ、施術や運営をスタッフで分担できる体制を整えることが、売却価値を高める鍵になります。引継ぎ体制の明確化やマニュアルの整備なども、属人化リスクの低減に寄与します。
POINT 04継続性を意識した運営スタイルの見直し
買い手が重視するのは「買収後も安定して収益を上げ続けられるかどうか」です。日々の業務が特定スタッフのスキルや関係性に依存していないか、サービスが一定品質で提供されているかなど、持続可能な運営体制を整えることが求められます。可能であれば、売却後も一時的に経営に関与する「引継ぎ期間」について検討しておくと、さらに好条件での売却が狙えます。
07接骨院・整体院M&Aの流れと進め方

接骨院・整体院のM&Aは、専門的な知見と慎重な手続きが求められます。、売却に至るまでの一般的な流れと、それぞれのステップで押さえておくべきポイントをご紹介します。
STEP 1相談
まずは専門機関やM&Aアドバイザーに相談し、売却の目的や希望条件を明確にします。現状の院の価値や、売却後の選択肢について意見をもらうことで、方向性が整理されます。
STEP 2査定
店舗の財務状況、設備、人材、立地条件などをもとに、企業価値を査定します。多くの場合、「営業利益の2〜5年分」や「純資産+利益の数年分」などを目安に査定額が算出されます。
STEP 3交渉相手の選定
希望条件に合う買い手候補を探し、候補者・候補企業へ匿名で概要資料を提示します。この段階では院名や所在地など、特定につながる情報は伏せるのが一般的です。
STEP 4条件交渉
候補先から興味を示された場合、秘密保持契約を結んだうえで詳細情報を共有し、トップ面談などを経て条件交渉を進めます。
STEP 5契約
基本合意がまとまった後は、買い手によるデューデリジェンス(調査)を経て、最終的な譲渡契約を締結します。賃貸物件やリース設備、スタッフ雇用契約などの引継ぎもこの段階で整理します。
STEP 6売却実行(クロージング)
契約書に基づき、資産や権利の移転、代金の受け渡しなどの実務を行います。株式譲渡の場合は名義変更や登記、事業譲渡の場合は契約や許認可の引継ぎなど、法的な手続きが必要です。
期間の目安
M&Aの実行までは通常3ヶ月〜半年程度を要します。買い手選定や条件交渉、必要資料の準備状況によって前後しますが、余裕を持ったスケジューリングが成功のカギです。
08よくある質問
Q. 赤字でも売却できますか?
条件次第では、赤字でも売却は十分可能です。
M&Aの実行までは通常3ヶ月〜半年程度を要します。買い手選定や条件交渉、必要資料の準備状況によって前後しますが、余裕を持ったスケジューリングが成功のカギです。
Q. スタッフや患者さまにはいつ伝えるべきですか?
通常は「契約締結直後〜クロージング直前」に伝えるのが一般的です。
M&A交渉の初期段階で公表すると、従業員の不安や離職、患者さまの動揺を招くリスクがあるため、情報公開のタイミングは非常に重要です。主要スタッフや管理職など、事前に理解と協力が必要なキーパーソンには早めに伝えることもありますが、全体への正式な案内はクロージング直前が最も多く採用されています。
Q. 個人経営の院でも買い手は見つかりますか?
はい、個人経営でも買い手が見つかる事例は多数あります。
特に後継者不在やライフスタイルの変化などで事業承継が必要なケースが増えており、個人院のM&Aも活発になっています。買い手は、独立を目指す施術者、エリア拡大を狙う法人、異業種からの参入企業など多岐にわたります。プラットフォームやM&A仲介を活用することで、より広い層へアプローチすることができます。
Q. 許認可や保険請求は引き継げる?
引き継ぎには再申請手続きが必要です。
施術管理者の変更に伴い、「開設届」「受領委任契約」などを新たに提出しなければなりません。買い手側が柔道整復師などの国家資格を持ち、必要書類(資格証・研修修了証等)を整えることで、申請が可能になります。保険請求の継続には地方厚生局との再契約が必須であり、M&Aスケジュールに余裕をもって準備を進めましょう。
Q. 譲渡先は何を基準に決めればいいですか?
条件だけでなく、「相性」や「直観」も大切な判断材料です。
譲渡先の選定においては、もちろん提示された価格や条件面も重要ですが、それ以上に「信頼できるか」「考え方が合うか」といった相手との相性が大きな意味を持ちます。
「金額は少し希望に届かないけれど、この人なら安心して任せられる」と感じるような直観も決断のうえで無視できない要素です。買い手の人柄、社風、今後の運営方針などをしっかり確認し、自院の理念やスタッフとの相性も含めて総合的に判断しましょう。もし譲渡先のイメージが湧かない場合や判断に迷う場合は、M&Aの専門家に相談してアドバイスを受けるのも有効です。第三者の視点が加わることで、見落としていた価値やリスクに気づける可能性もあります。
09まとめ

接骨院・整体院の売却は、経営者としての大きな判断であると同時に、今後の人生設計にも深く関わる選択肢の一つです。どのような形で院を引き継いでもらうか、どの部分を残し、活かしてもらうかを丁寧に見極めることが重要になります。
私たちは、接骨院・整体院に特化したM&A支援を通じて、経営状況だけでなく、院の雰囲気やスタッフ・患者さまとの関係性といった「見えにくい価値」まで含めて、納得度の高いマッチングをサポートしています。
「今すぐの売却は考えていないけれど、将来に備えて情報だけ集めておきたい」という方も歓迎しています。選択肢の一つとしてM&Aを視野に入れることは、経営者自身の将来への備えにもつながります。
まずはお気軽に無料相談をご活用ください。